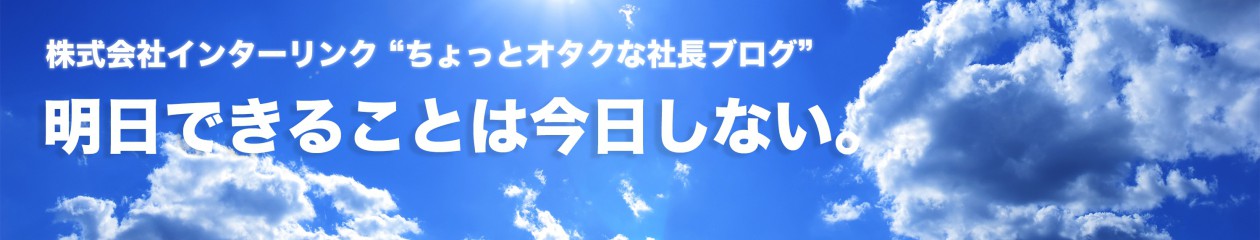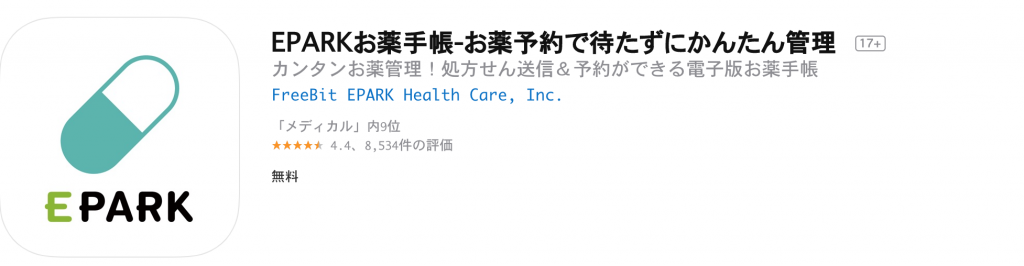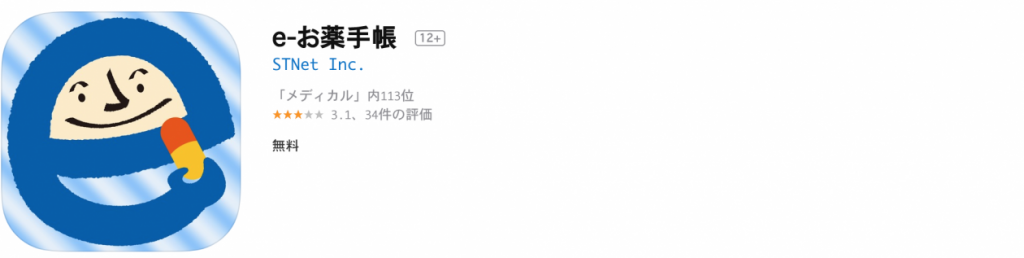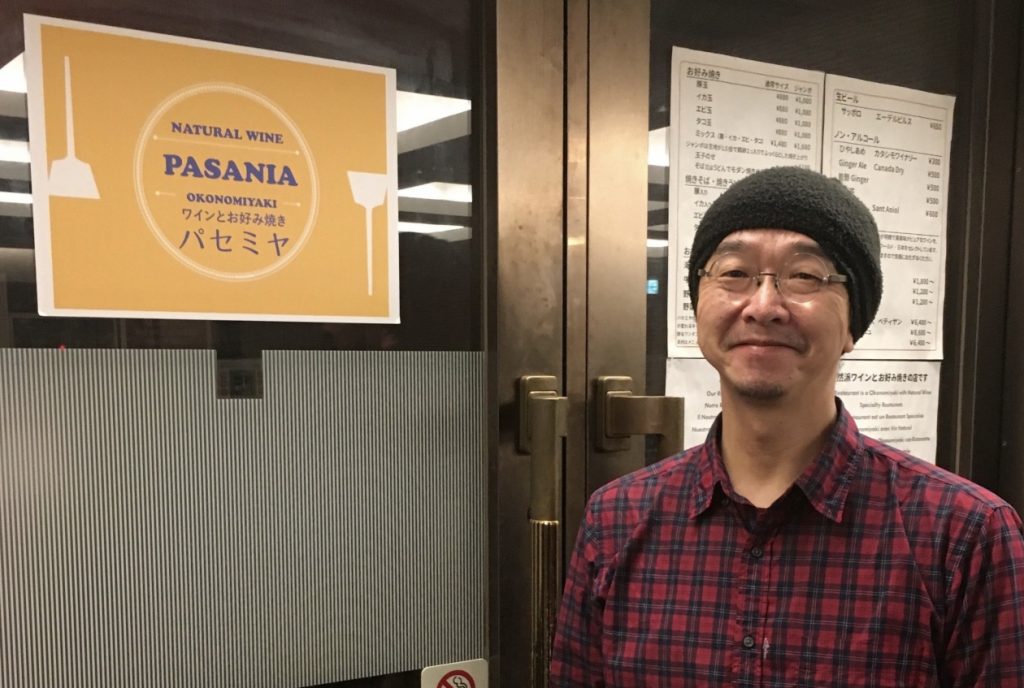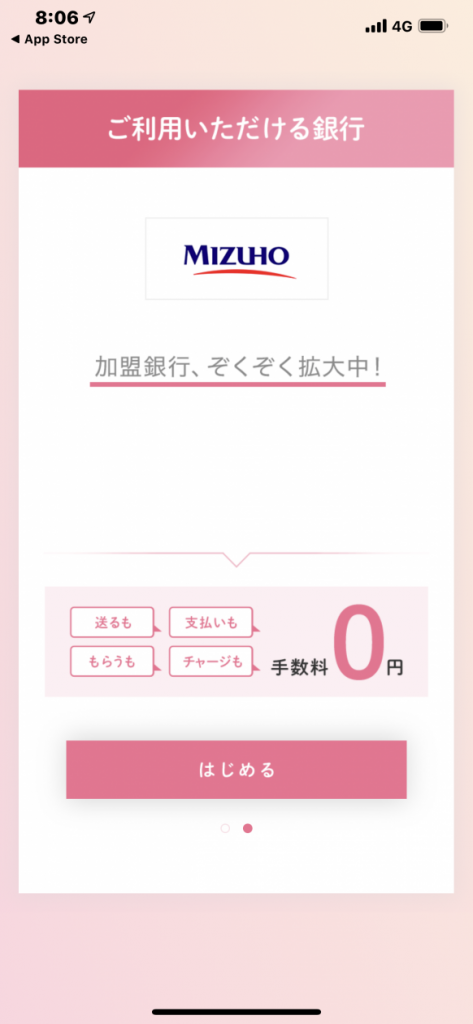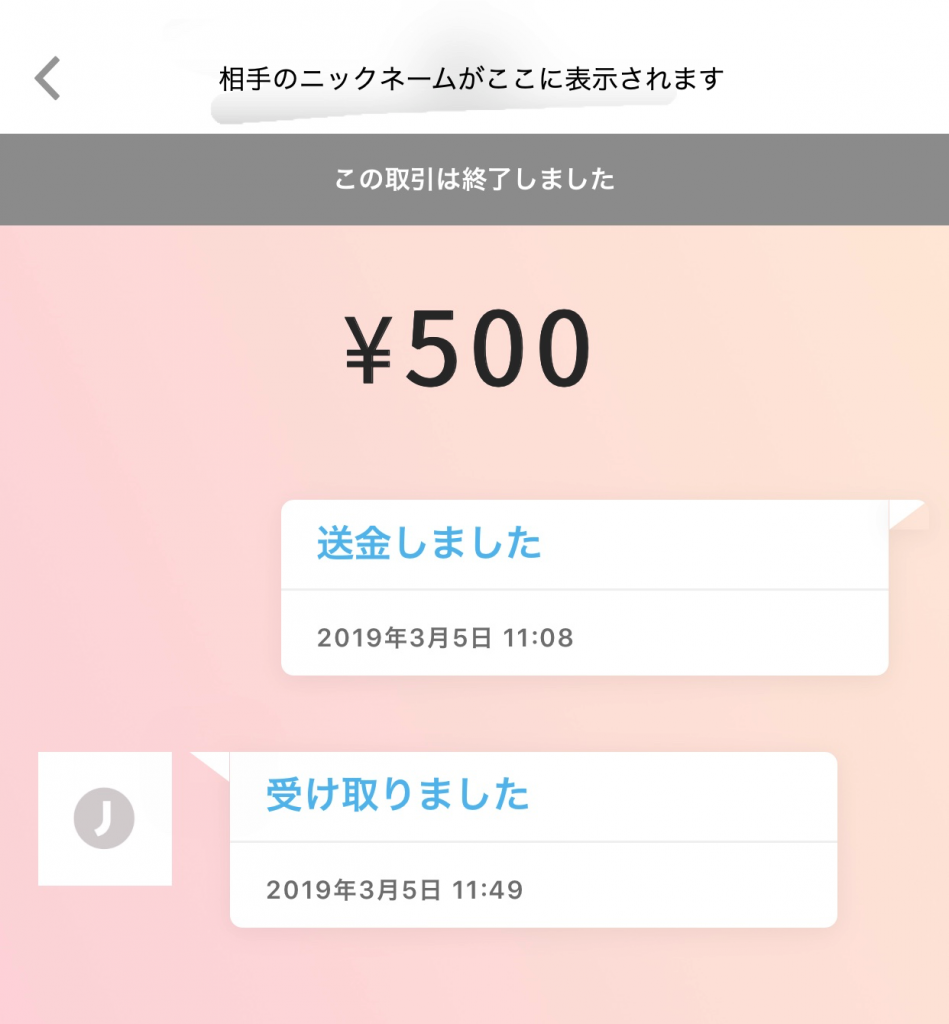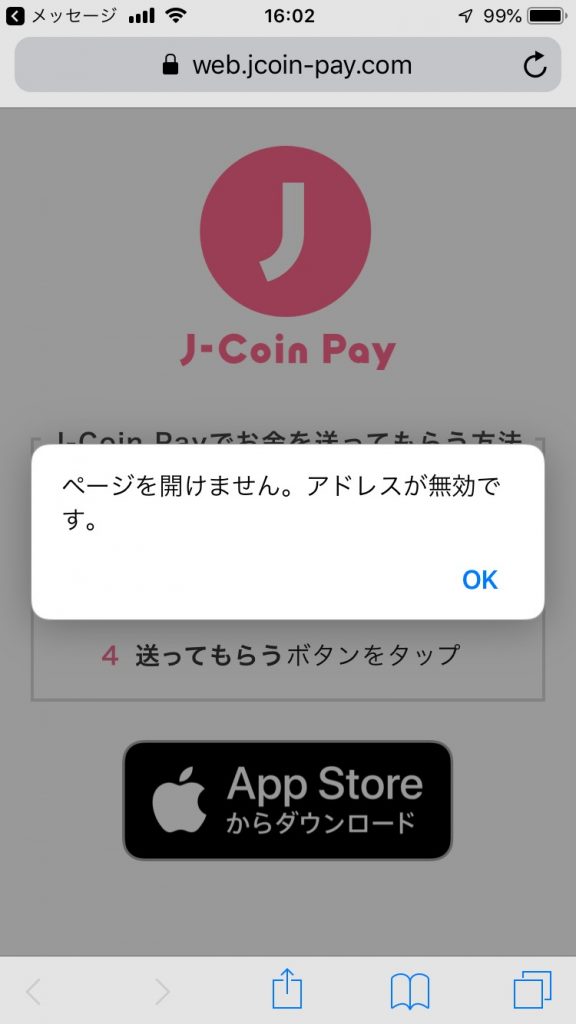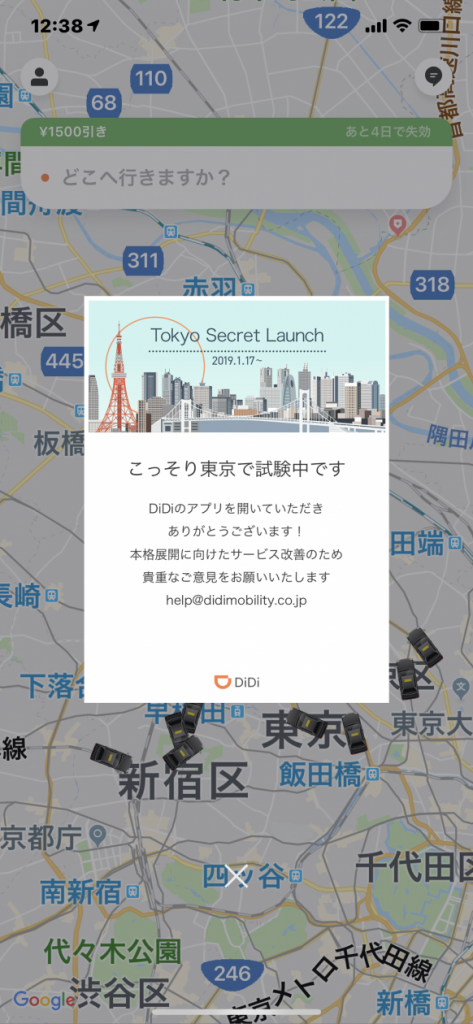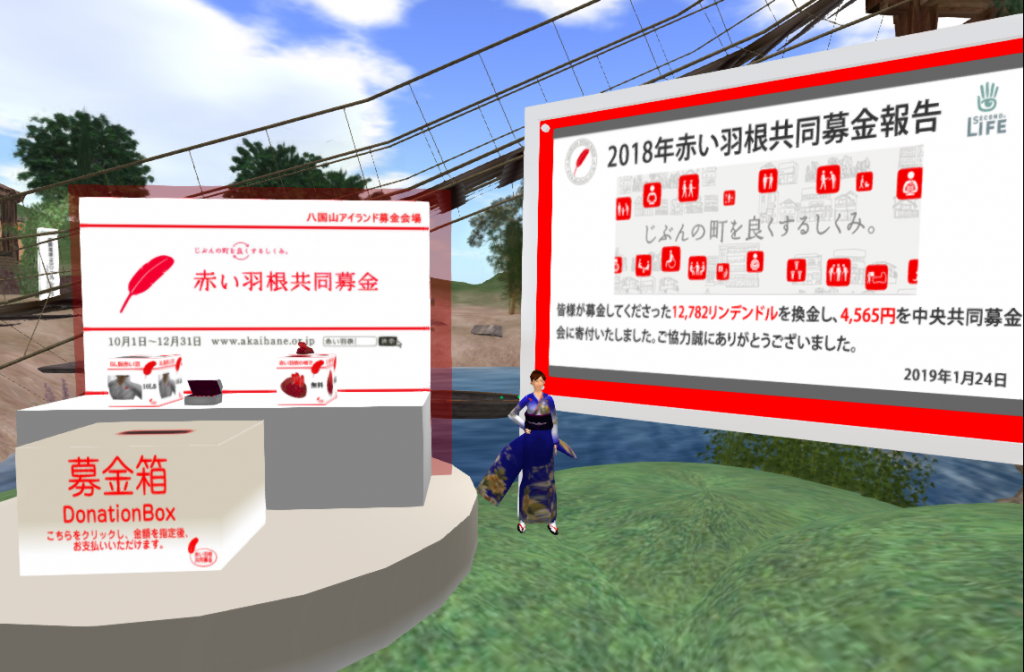ビジネスは、お互いに競い合って切磋琢磨する、という場面と、同業者が力を合わせて、業界を盛り上げるために協力するという場面が交錯します。
同じ会社が、ある時は、敵だったり、ある時は、味方だったりするわけです。
今は、オンライン決済がアツいですね。
Paypay、LINE Payが大規模なキャンペーンを張っている中、メルペイがGW中にすごいキャンペーンをやっていました。
しかも、セブンイレブンは70%還元だったのです。
こういう同業者同士のキャンペーン合戦のような競争は、ユーザーにとってはうれしいですね。
でも、うれしくない競争というのもあるんです。
それは
…………………………………
…………………………………
…………………………………
お薬手帳アプリの競合です。
会社のあるサンシャインビル内の薬局で薬を待っていたら、お薬手帳アプリの宣伝が目に入りました。
これは便利!と思って、お薬手帳アプリを入れました。
QRコードでお薬を読み込めて、すごくいいなと思っていました。
ところが、ある時、別の病院で処方箋を出してもらい、別の薬局で薬をもらったのですが、その薬局は、EPARKお薬手帳に対応しておらず、別のアプリが必要になりました。
それが、e-お薬手帳です。
お薬手帳アプリは他にもたくさんあり、乱立していて、1つだけで済ませられない状況です(手入力や写真撮るなどすれば1つで済ませられますが、さすがに面倒です)。薬の情報が複数のアプリに散らばっていては、お薬手帳の意味が半減してしまいます。
こういう競争は、ユーザーにとってメリットがないので、ぜひとも薬のQRコードを共通化して、どのアプリでも読めるようにするなど、競争だけでなく、業界内で協力もしてほしいと思った次第です。