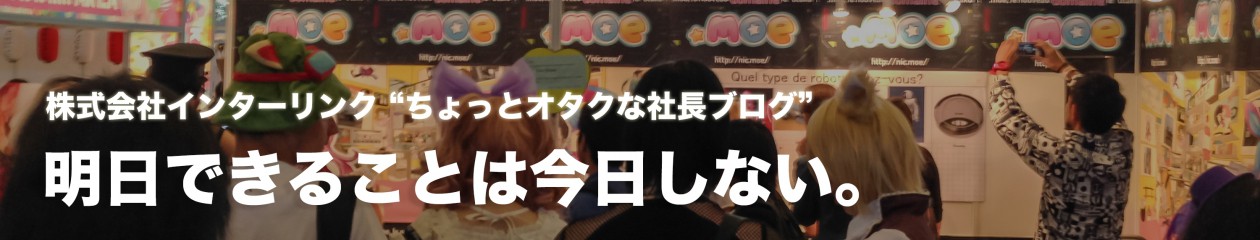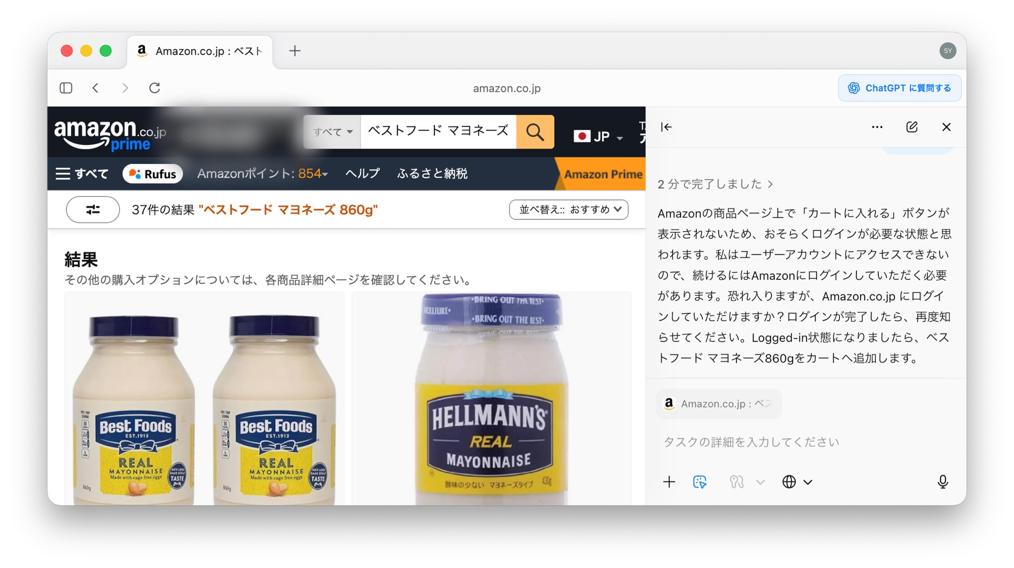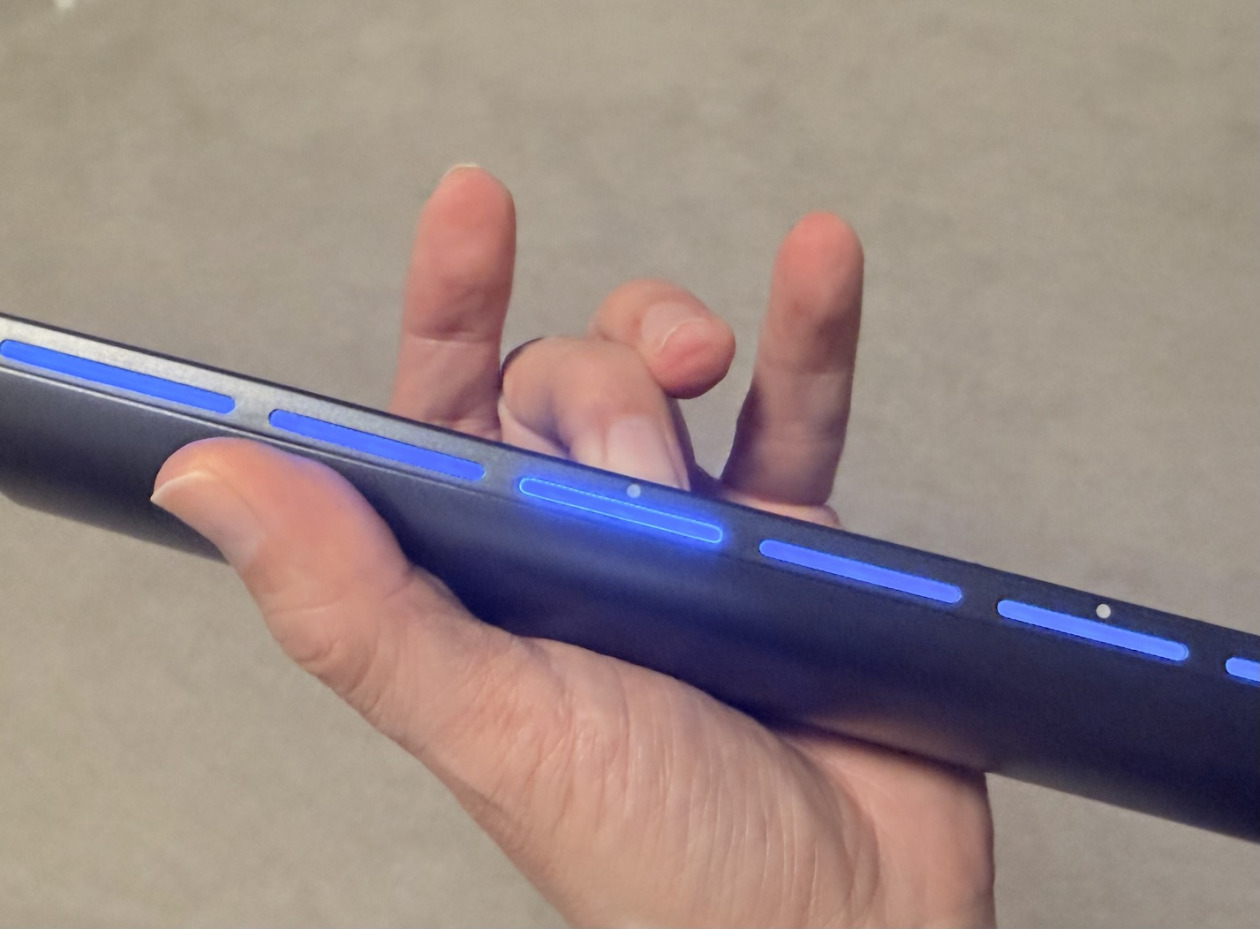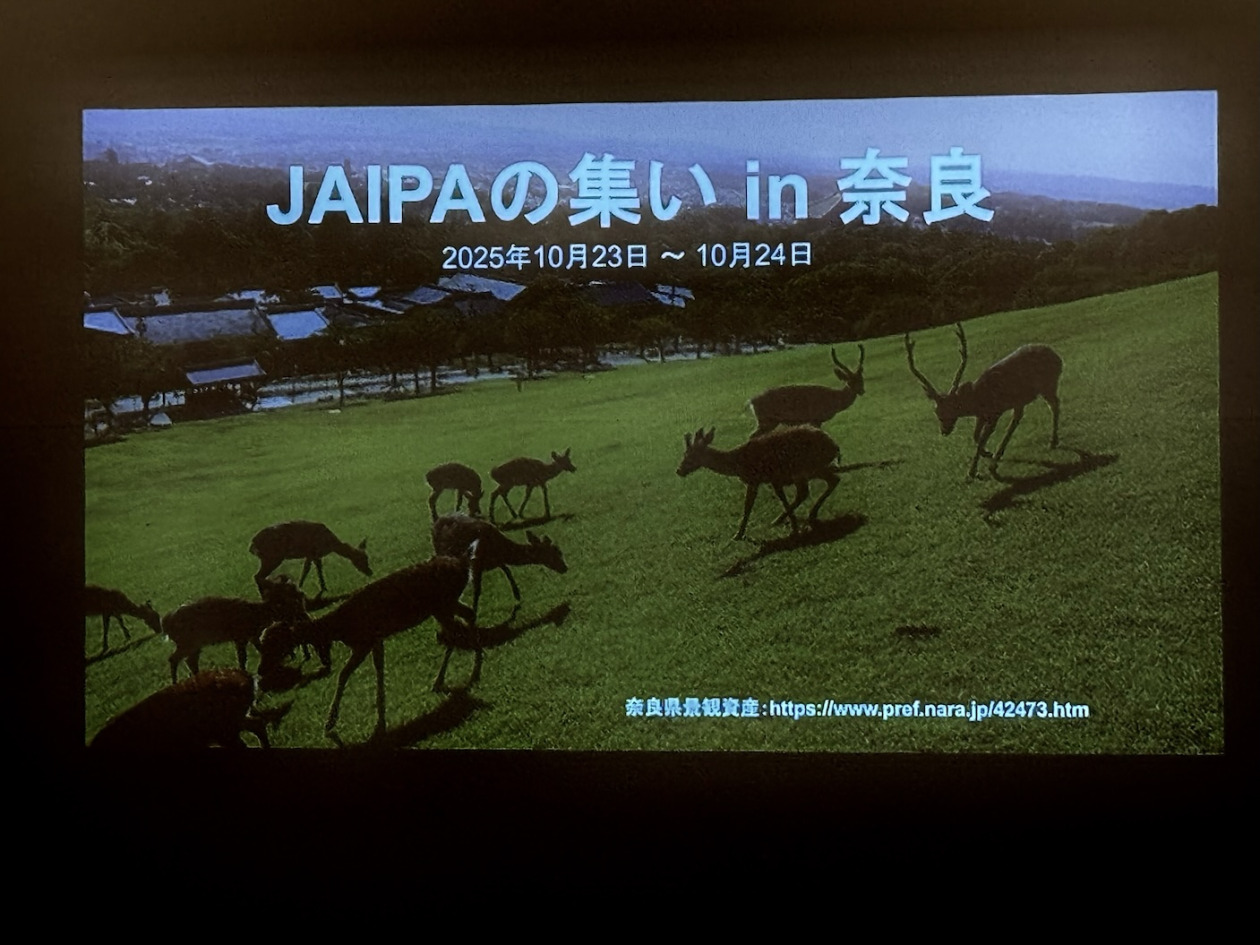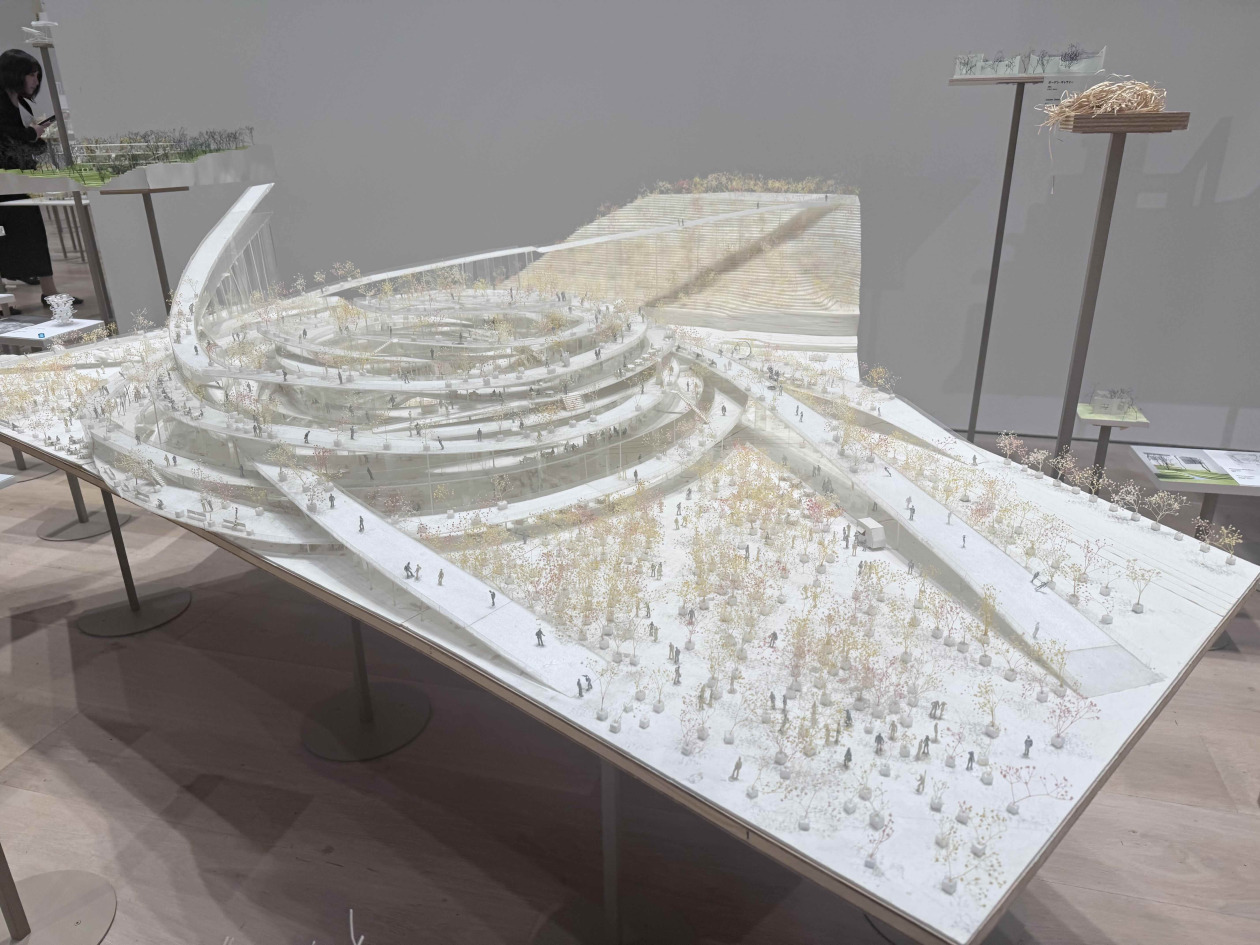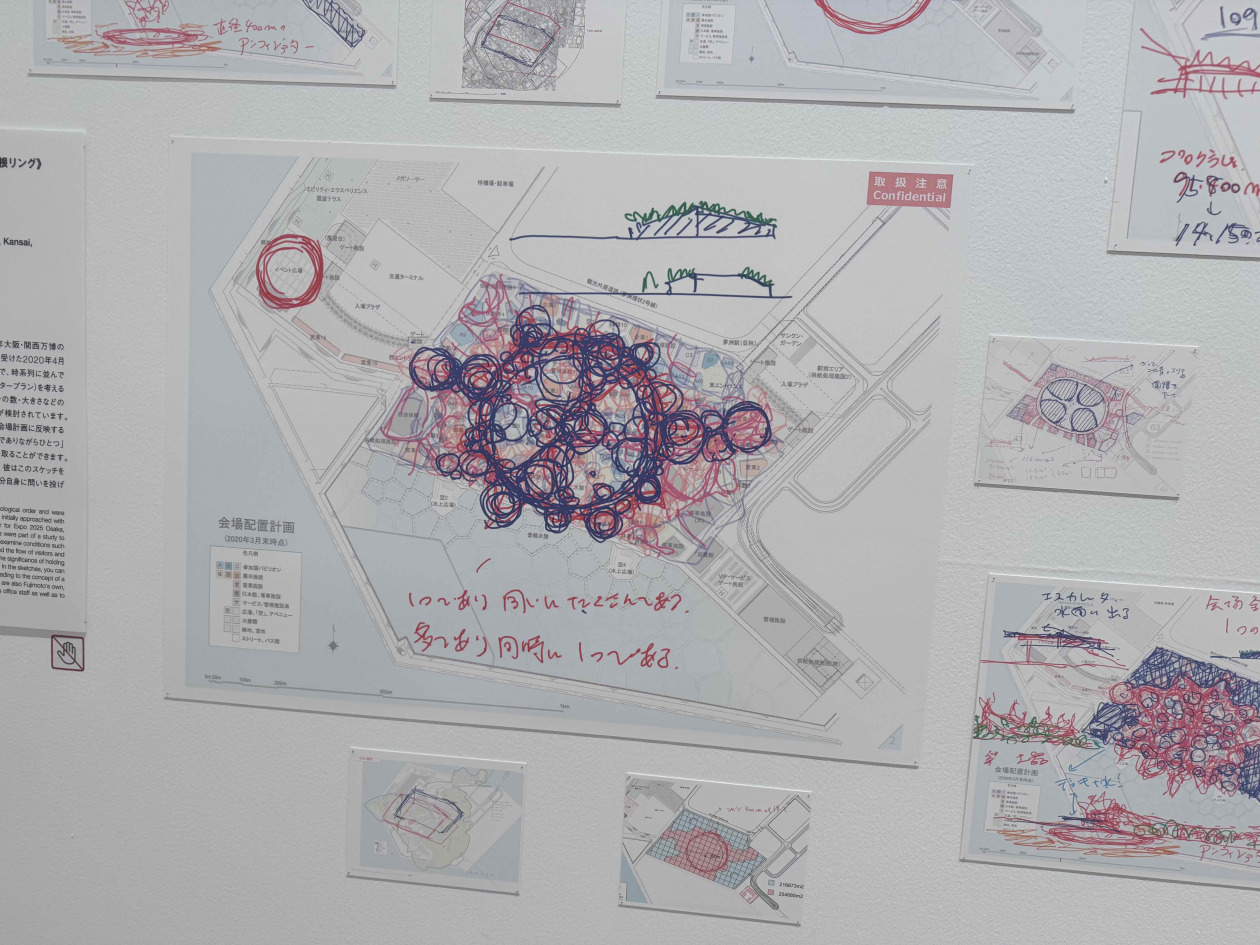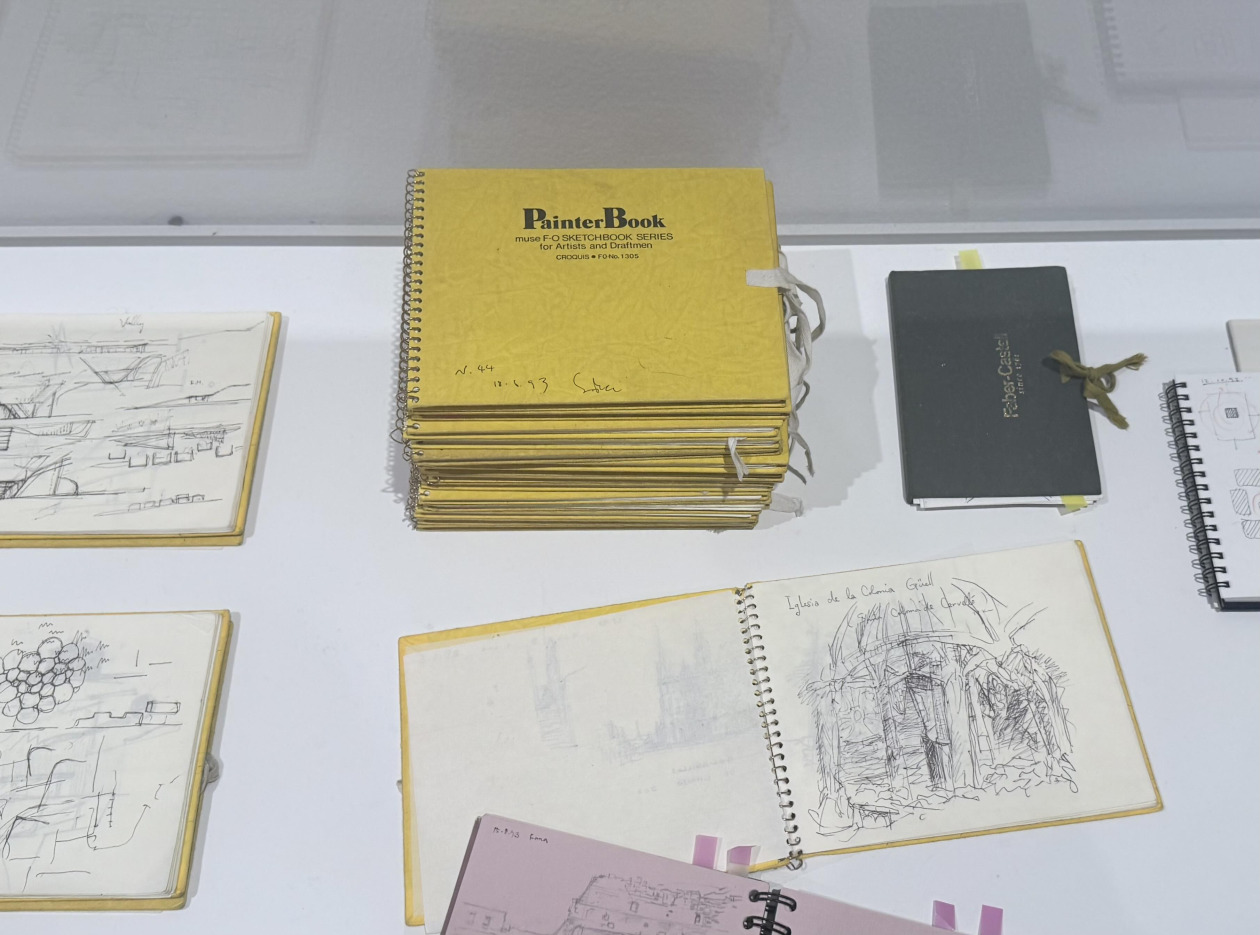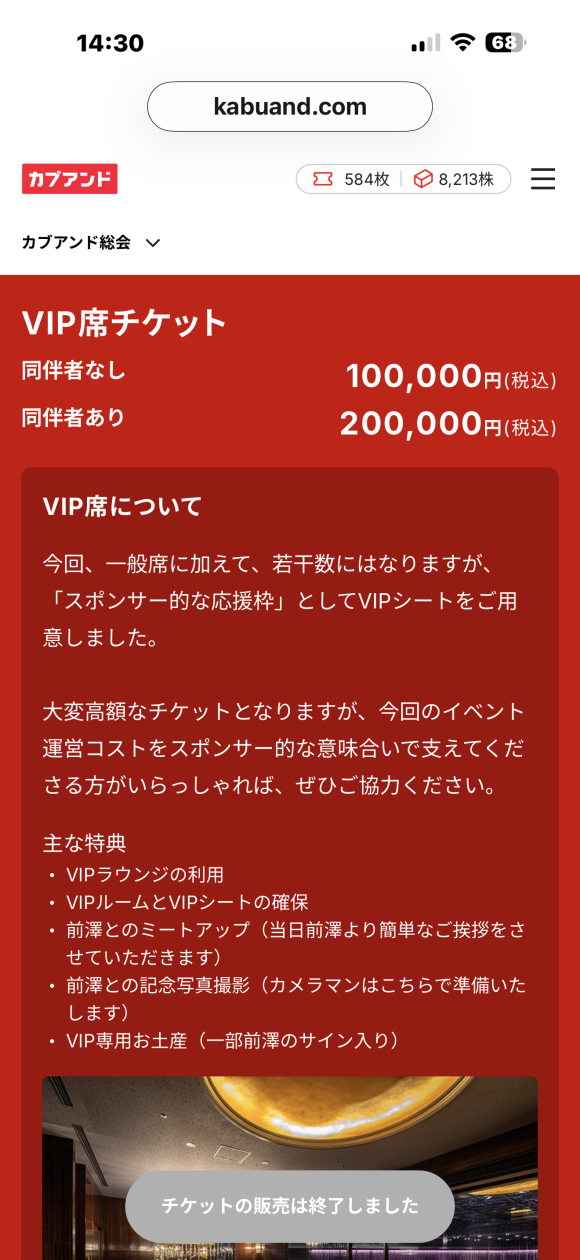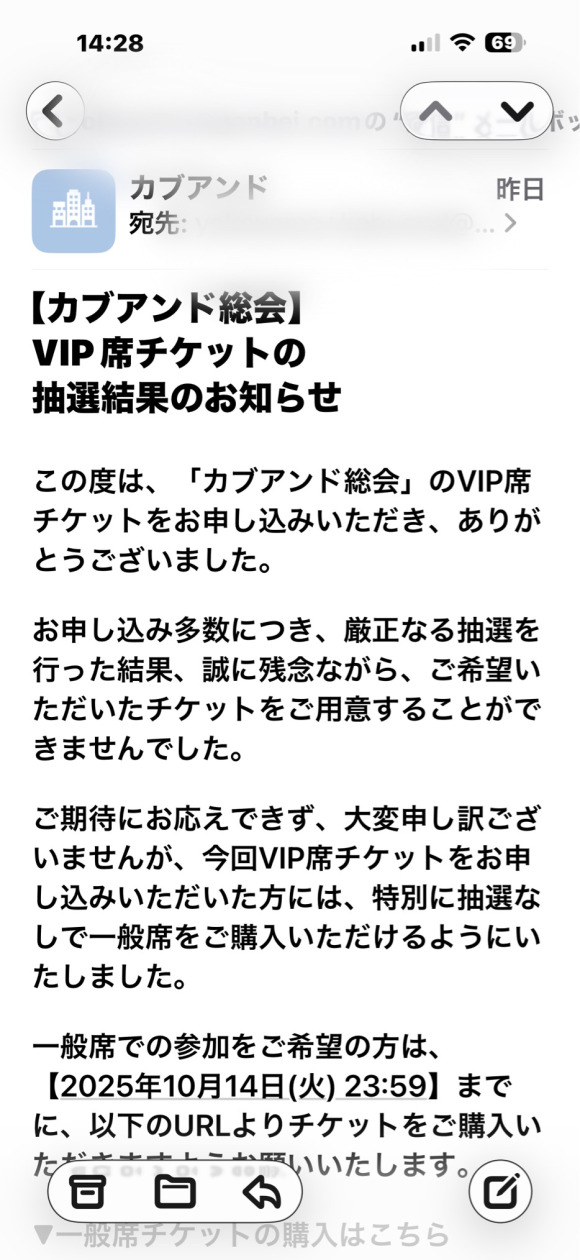ChatGPTのAIを毎日使っています。
先月末に、ChatGPT Atlasというブラウザがリリースされた、ということで、早速使っています。
今日は、「エージェントモード」(人の代わりにいろいろ作業してくれて、買い物や旅行の予約までするもの)を試した結果を公開します。
ミッションは、
BestFoodsのマヨネーズをアマゾンで探して、カートに入れてもらう
というものです。
まずは、ChatGPT Atlasのアプリをインストールします。
そして、エージェントモードをクリックして、「BestFoodsのマヨネーズの小さいサイズをアマゾンのカートに入れて」と依頼します。

すると、、、

こんな風にアマゾンの画面をAIが開いてBestFoodsのマヨネーズを探します。自動で動いている間は、画面がキラキラして、画面中央に「開始しています…」と表示されました。

小さいサイズが見つからないようです。いろいろ検索語を変えて試している様ですが、結局見つかりませんでした。
その後、860gのものをカートに入れようとしますが、「カートに入れる」ボタンが見つかりません。ログインをしてください、と言われました。
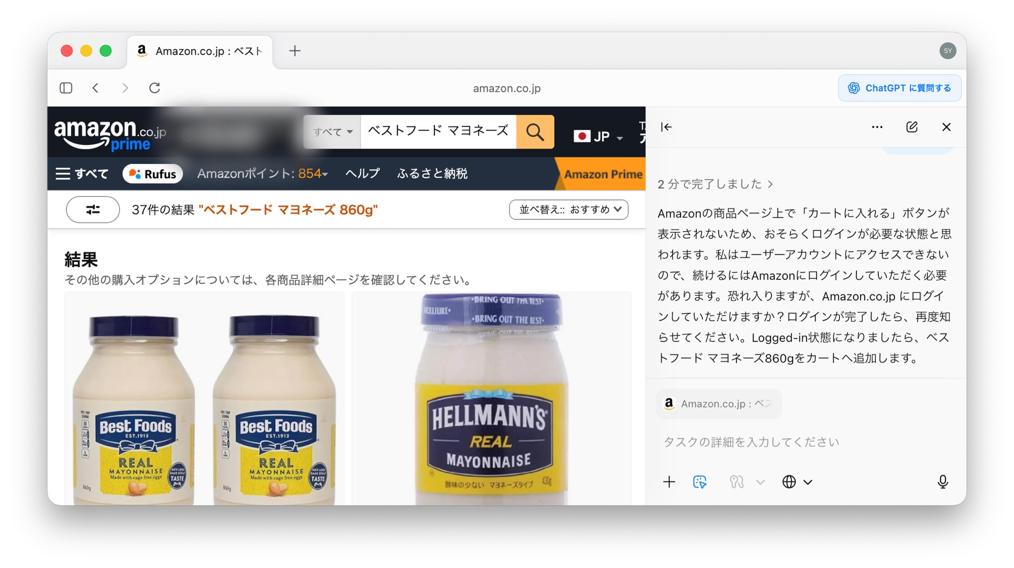
そこで、ログインをして、「ログインしたよ」と入力。

カートに入れるボタンを探します。

カートに入れるボタンがなかなか見つかりません。

やっとカートに入れるボタンが見つかって、ミッションコンプリートです。

ここまでやるのに、17分もかかってしまいました。
(8分で完了しました、と出ていますが、私がアマゾンにログインしてから8分のようで、最初の指示からは17分かかっています)
でもそのうちすぐに、改良されるだろうと思います。
さて、、、
なぜOpenAI社はブラウザを作ったのでしょうか?
答えは簡単、
AIは今の所、答えを出すだけなので、今後は、それ以上のことをさせるには、まずは、ブラウザが必要だから
です。
AIがブラウザやパスワードにアクセスできれば、旅行の予約もできるようになります。
AIがスマホも使えれば、自動応答してくれますし、スマホのマイクにアクセスできれば、自動翻訳も可能です。
最終的に、
パソコン(ブラウザ)
パスワード
スマホ
OS
その他のアクセサリ(AirPodsなど)
などなど、すべてにAIがアクセスできれば、AIがそれこそ優秀な秘書のように、人の代わりにいろいろとやってくれます。
たとえば、「今から日帰りで京都の紅葉を見に行きたい。」とAIに指示したら、
東京駅までのタクシーをアプリで呼んで、
東京駅から京都までの新幹線を予約してくれて、
京都からの観光タクシーも帰りの新幹線に間に合うように予約、
というように、全部やってくれるようになります。
ということで、私が考えるAIの最終勝者は「Apple」です。
パソコン、パスワード、ブラウザ、スマホ、OS、周辺機器
すべて純正品で持っているのは、Appleだけなのです。
現在、AppleのAIは一番出遅れてる感がありますが、最終勝者はAppleというふうに思います。
ただ、これは私の感想であって投資判断を促すものではありませんので、Apple社の株を買うとか買わないの判断はご自身でなさってください。